地道な継続にこそ成果は現れる
- 金本 淳
- 2021年9月14日
- 読了時間: 7分

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
心動かす企業経営 vol.273
=================
<地道な継続にこそ成果は現れる>
おはようございます。
フェリーゼス経営支援事務所の
金本淳(かねもとあつし)です。
「経営を改善したい!」
という想いから新たな取組みを始めた。
でも、数回やっただけで、
その後続かなくなる。
そういう事ってよくありますよね。
せっかく、色々考えて出したアイデア。
その時は「是非やってみよう!」と
意気込んでいらっしゃったと思います。。
初めてお会いする経営者様への
ヒアリングで、私が
「これまで、どんなお取組みを
されてこられましたか?」
と、お伺すると
「あれもやりました。」
「これもやりました。。。。」
といくつか取り組んだことについて
お話をしていただけます。
また
「○○はやられていますか?」
とお尋ねすると、
「あー、それは前にやってみました。」
というお答えが返ってくることが
よくあります。
「それで効果はありましたか?」
と聞くと、大概
「うーん、どうでしょう。。。」
というようなご返答をいただきます。
「どれくらい(頻度、期間、回数)
やりましたか?」
と聞くと、大抵、1,2回、
多くて4、5回程度との回答が
返ってきます。
ではなぜ、やり始めたことを
数回でやめてしまうのでしょう?
よくよく聞いてみると、
「忙しくてついつい後回しに
なってしまった」
「他にすぐにやらなければならないことが
沢山あり、そちらに忙殺されている間に
出来なくなった」
など。
例えば、先回書いた、
「お客様との関係性づくり」
なんかもそうです。
自社のファンになってもらうために、
しっかりアフターフォローをやろう
ということで取組を始めた。
でも、今お店に来ている新規のお客さんの
対応のほうが忙しくて、結局、
一度来てくれた既存のお客さんへの
アフターフォローが疎かになる。
そういうことを繰り返しているうちに、
環境変化が起こり新規のお客さんが
来てくれなくなった。
例えば、景気が悪化した。
あるいは、近所に競合店が出店し、
そこに新規のお客さんをとられるように
なったなど。
でも、その時はもう手遅れです。
新規客が来てくれないばかりか、
既存客も何もケアされずに放って
おかれたので、リピーターになる人も
あまりいなくなってしまっています。
かと言って、そこからまた新規顧客を
獲得していくのも大変です。
元々、新規顧客を獲得するためのコストは
既存顧客に再来店してもらうための
コストの何十倍もかかると言われています。
だから、そうならないように、
一度来店してくれた既存客をしっかり
フォローして、リピーターになって
もらわなければなりません。
そして、これはお店だけでなく、
どんな企業でも同じでしょう。
基本は、既存客のリピーターで
回していける体制を構築する。
そうは言っても、既存客も色々な事情で
どうしても来店できなくなり徐々に
減っていく。
だからそれを補うために、
既存顧客一人当たりの単価を増やす、
あるいは、新規顧客を獲得する。
そういう感じの事業構造をつくり
回していくことが理想なのだと思います。
でも、多くの企業は、足元の取組みに
忙殺されると、どうしても
長期的にやらなければならないことが
疎かになってしまう。
まあ、これは人間の心理として、
ある程度仕方のないことなのだと
いう事も十分承知しています。
やはり、誰だって、いつ成果が出るか
わからないものより、足元の成果を
重要視しがちになってしまいます。
ただ、ご理解いただきたいのは、
こういうことです
多くの取組みはそうだと思いますが、
わずか数回の取組みで、簡単に成果が
出るようなものってあまりないのでは
ないでしょうか。
それは、スポーツや趣味などが
上達していく過程とも似ています。
特に、人材育成、顧客育成、
組織・風土づくりなど、
会社の事業基盤となるしくみづくりという
取組に関して言えば、どれも長い年月を
要するものばかりです。
しかもそういうしくみこそが、企業活動の
強さの源となる重要なものなのです。
継続した物事の成果って、
やった回数に比例する。
つまり横軸が回数(時間)、
縦軸が成果、としてグラフを描くと、
左下の原点を起点に右肩上がりの直線に
なると思うかもしれません。
でも、実際はそんなに単純では
ありませんし、甘くもありません。
知ってる方もいらっしゃるかと
思いますが、こんな風になると
言われてます。
最初は殆ど成果が出ずに横ばい、
そしてそれがしばらく続きます。
ようやく成果が少し出始めるのが、
グラフの半分以上、あるいは
4分の3くらい過ぎたところ、
そして、最後
そこから一気に上昇するという曲線です。
回数はどれだけというのは、
ケースバイケースなので
誰にもわかりません。
でも少なくとも数回で成果が出る
というものは、殆どないでしょう。
また、数回で成果が出るものとなれば、
競争相手は誰でもやっているものとも
言えるでしょう。
だからやってもその他と同等、
当たり前というレベルで、優位性を
持つことにはならないということです。
このように、
本当に強い企業を作っていくには、
時間が必要なのです。
成果を出すには時間がかかることを
継続して取り組む姿勢が必要なのです。
いつ実るかわからない成果を待つのは
誰もが苦しいでしょう。
でも、それを乗り越えて、
続けられる忍耐力を持てるかどうかが、
最後に企業の明暗を分けるのだと思います。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
<今日のありがとう>
本当は面と向かって伝えたい
でも中々言えない自分がいます
=================
私はトヨタで働いていた時、
一番所属していた期間が長かったのが、
アフリカ部という部署です。
おかげさまで、普通の人があまり行かない
アフリカの国々の人たちと仕事ができる
という貴重な機会をいただきました。
それだけでも先ずは感謝です。
さて、そんなアフリカ部に所属していた
メンバーのZOOM飲み会&
Aさんの会社生活退任祝いの会が、
この前の週末にオンラインで
開催されました。
参加者31名と大規模な会でした。
Aさんには、退任祝いというのは
隠していて、サプライズ企画を
幹事の人たちが考えてくれていました。
プレゼントや寄せ書きの
贈呈に始まり、
その後ビデオ上映です。
昔の懐かしい写真
そして、Aさんは南アフリカトヨタの
日本人トップを務めていらっしゃった方
なので、その頃にかかわっていた
現地スタッフからのメッセージ、
さらに、Aさんのご家族からの
ビデオメッセージなど
それらが、一つの動画作品として
編集されたものがZOOMで
上映されるという、感動ものでした。
また、久しぶりに元気な声を聞けた方も
いましたし、本当に素晴らしい会でした。
昔、苦楽を共にして、頑張った仲間との
繋がりというのは、いいものだなあと
いうことを改めて感じました。
また、そういう縁に恵まれた自分も
幸せなのだなあということを
しみじみと感じました。
そんな素敵な会を企画してくれた
幹事の方々には感謝しかありません。
「ありがとうございました!」
最後までお読みいただき
ありがとうございました。
今日も素敵な一日になりますように!
◆読者からの励ましの声が、
何よりもエネルギーになります。
あなたからの感想・コメント、
お待ちしています。
お気軽に、コメントください
info@feli-zes.biz
【本メルマガについて】
このメルマガは、
・働く人のヤル気であふれ
活き活きと働ける職場を作りたい
・働く人が持てる能力をフルに発揮しながら
成長してもらいたい
・成り行きではなく明確なビジョンを
持って、経営を進めたい
・経営者と従業員がそのビジョンに向かって
一体となって進んでいきたい
・仕事を通じて世の中に貢献したい
そんな中小企業経営者の皆さまや
企業経営に関わる方々にお役に立てれば
という想いで発行しています。
このメルマガでは、
自分自身のサラリーマン時代の経験や
実際のコンサル現場での経験などから、
日々感じたことを情報発信
させていただきます。
その中で、ワクワクドキドキ心動かす
企業・お店づくりのヒントを提供しながら、
お役に立ちたい。
そして自分自身も一緒に豊かな人生を
目指して成長していきたいと考えています。
メルマガへの想い詳細はこちら
https://www.felizes.biz/mailmagazine
◆フェリーゼス経営理念◆
ワクワクドキドキ、
働く人の人生を豊かにする
コンサルティング
◇フェリーゼスミッション◇
経営者と従業員が、
毎日会社に行くのが楽しみで仕方がない
ワクワクドキドキで一杯の
中小企業づくりをサポートします!
ご興味ある方、詳細はこちら
https://www.felizes.biz/aboutus
【公式サイト】
https://www.felizes.biz/
【個人Facebook】
https://www.facebook.com/atsushi.kanemoto.9
【公式ブログ】
https://www.felizes.biz/blog
(過去のメルマガもアップしています)
***************************************
心動かす企業経営
【発行元】フェリーゼス経営支援事務所
【発行責任者】金本 淳
経済産業大臣登録 中小企業診断士
豊田市働き方改革アドバイザー・講師 国際ファッション専門職大学非常勤講師
【住所】
〒480-1161愛知県長久手市荒田1-1-718
【お問い合わせ】 info@feli-zes.biz
=========================














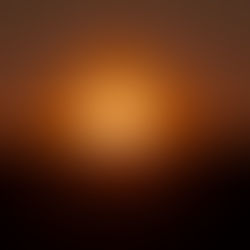









コメント