人を正しく評価するには?(解決編)
- 金本 淳
- 2021年11月19日
- 読了時間: 9分

(2013年12月 大阪大泉緑地)
皆様に幸運が訪れますように!
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
心動かす企業経営 vol.292
=================
<人を正しく評価するには?(解決編)>
おはようございます。
フェリーゼス経営支援事務所の
金本淳(かねもとあつし)です。
今回は先回の続きです。
先回、評価の難しさについて
お話ししました。
評価は、放っておくと人それぞれで
色んな評価にわかれてしまう。
だから
「評価に満足していない」
という従業員が多い。
その一方で、評価する側は、
自分の尺度を持って評価しているので、
自分の評価は正しいと思っている。
だから経営者は、
「従業員は評価に満足しているはずだ」
と思っている方が多い。
今回は、この厄介な評価を
正しい評価にするには
どうしたらいいでしょう?
ということについてです。
と言いながら、
実は私はこう思っていますが。。
それは
「正しい評価なんてものはないのでは?」
ということです。
と言いますのも
先回も書かせていただいたように、
評価は人によって必ず差が出るのが
当たり前だと思うからです。
評価する側と評価される側の関係性、
評価する人の性格やものの見方など、
それぞれの人がこれまでの人生で
培ってきた色々な要素が重なり、
違いというものが絶対に
出てくるのだと思うのです。
例えば、
普段から親密な関係性であれば、
情もわくでしょうし、
どうしても甘い評価になります。
また、人を厳しく評価するのが嫌な人は
甘い評価を下すでしょう。
そして、その逆も然りです。
また、その他にも評価の差異を生み出す
要因はたくさんあります。
ということで、
先ず、この問題を考える際に認識して
おかなければならないのは、
「人間が評価する限り、全く同じ評価には
なり得ない」
ということだと思います。
ただ、こう言ってしまうと、
話が終わってしまいます。
でも一方で私はこうも思うのです。
「正しい評価はできないかもしれない。
でも正しい評価に近づけることは
できるのでは?」
と
もう少し正確に言うと、こういうこと。
評価する側、される側が、
お互いに近い認識
(=何とか納得できるレベルの評価)
には近づけることができるのでは?
ということです。
では、人による評価のバラツキを
できるだけなくすには、
どうすればいいのでしょうか?
それを考えてみたいと思います。
私が考えるのはこのようなやり方です。
一つ目は、
「評価項目を明確にすること」
だと思います。
そもそも評価といった場合、
何を評価するのか?
という評価項目が必要だということです。
もしあなたが、
「Aさんを評価してくれ」
と頼まれたらどうでしょうか?
Aさんは頼んだ仕事は速いし
中身もバッチリ。
でも他の社員を助けたり、協力して
何かをやるということはやらない。
個人プレーばかりで他の社員からは
評判がすごく悪い。
仕事が速くて優秀な面だけ見ると、
評価は高くなります。
でも他の社員への影響を考えた場合、
会社にとってはマイナス面もあるのです。
そうなると、
どう評価するか難しいですよね。
こういう場合に、やはり、
何を評価するかというのが
はっきりしていれば、
評価もしやすいでしょう。
例えば、
仕事の正確さ
仕事の速さ
協調性
など
ふたつ目は、評価の基準です。
上に挙げた評価項目を
どう評価するのか?
ということです。
「仕事の正確さや速さ」
と言っても、
どうなったら正確で
どれくらいの速さなら速い
と言えるのかって、わからないですよね。
「協調性」もそうです。
どうなっていれば協調性が高い
と評価できるのか?が問題です。
これを解決するには、基準を
定めることが必要じゃないかと思うのです。
例えば、「正確さ」で言うと
お願いした資料作成を
手直しが全く不要なレベルで作成できる
2割程度手直しすればよいレベルで
作成できる
半分以上、手直しが必要なレベル
など
より具体的になればなるほど
わかりやすいと思います。
そしてそれをみんなが共有すると
いうのも当然ながら必要です。
三つ目は、複数の人が評価すること
1人の人間だとどうしても評価が
偏ってしまうことは触れました。
これをできるだけ防ぐには複数で
評価するしかないと思います。
そして、四つ目
それは、評価した根拠を
被評価者に具体的に説明できるように
しておくことです。
例えば、
「A企業とB企業への提案資料は
完璧だった。
でもC企業は○○、D企業のは××だった。
だから、こういう評価なのです」と
そして、最後五つ目です。
そもそも
「どういう項目を
どういう基準で評価するのか?」
というのを、評価される人たちに
しっかり説明しておかなければなりません。
「会社があなたに求める能力は○○です。
○○について、××ならば評価はA」など
もっと言うと、
会社の経営ビジョンや経営計画と、
その期待する能力や知識・技能レベルが
リンクしている必要があると思います。
ただ、今回はそこまで突っ込むと
長くなるのでやめえときます。
色々書きましたが、
思うに、一番大事なのは、
「なぜこういう風になったのか」
というのをきちんと説明できるように
するということだと思います。
逆に、避けなければいけないのは、
自分達が、何をもって評価されているのか
わからない。
評価する側が評価の根拠をきちんと
説明できない。
という事態。
極端なことをいうと、
経営者1人が独断で評価をしたとしても、
その評価の根拠をきちんと
説明できさえすれば、
いいのかもしれません。
感覚的な評価で、理由を聞かれても
答えられない評価よりは、
経営者がこういう理由であなたの評価を
決めましたと言い切れるほうが
説得力があるように思います。
先程、複数の人が評価をする
というのを書きましたが、
評価する人、一人一人がきっちり
自分の評価の根拠を明確にする。
そして、それを評価した人たちの
間で、すり合わせをする。
そういったステップも
大事だと思います。
上司Xさん:
「私がAさんを○○と評価したのは
こういう事実からです。」
経営者Yさん:
「それはそうかもしれません。
でもAさんは、××に関しては、
できてないと思うよ。」
上司Xさん
「じゃあ、点数は1ランク下げます」
みたいな感じで評価者みんなで合意する。
上記の例は、紙面の都合で、簡易に
書きましたが、
ひとつひとつ、其々の根拠を
しっかり評価者間で話し合い、
最終的な評価と、その評価の根拠を
書面にして整理することが
必要だと思います。
そうすれば、少なくとも評価者側は
自信を持って、自分達の評価結果を説明
することができることになります。
当然、評価される側にも
言い分があるかもしれません。
でも、複数の人が、きちんと根拠を
持って、話いあいの末に判断した
ものであれば、公平性は保てると
思います。
それから、最後にひとことだけ
付け加えさせてください
それは評価の目的です。
私は、評価の目的は、あくまでも
従業員を育てるため
(=従業員の成長のため)
だと信じています。
給与や昇格は、従業員の成長の結果として
不随してくるものであり、評価制度の
直接的な目的ではないと思っています。
成長してもらうために、
会社の求めているものを提示し
それに対して、今自分がどの段階に
いるのかを見極めるのが
評価ではないかと。
そして、その評価をもとに
今より成長していくには、
どうすればいいのかを明確にして
取り組んでいく
そうやって従業員に
成長していってもらう、
評価はそれを支援する
一つのツールだと。
ということで長くなりましたので
この辺で終わりにします。
私の知る限り
現状、まだまだ多くの企業さんは、
「人を評価する」ということに
多くの課題を抱えていらっしゃるように
思います。
そういった企業さんに、今回の話が
少しでも参考になれば嬉しい限りです。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
<今日のありがとう>
本当は面と向かって伝えたい
でも中々言えない自分がいます
=================
水曜日に、知り合いのAさんが
本を出版されたということで、
その出版記念講演会に参加させて
いただきました。
Aさんは、定年されてからNPOでの活動を
通して、色々な取り組みをされています。
中でも子供の生活向上に向けた取り組みに
関してはものすごい力を注がれています。
ご自身の住む町の子供食堂の運営や
それを愛知県だけでなく全国に広げる活動
子供たちの個食、
子供たちの体験格差
を無くしていこうと
日々様々な取り組みに
ご尽力されています。
そのために
クラウドファンディングをやったり
日本初のコンビニを巻き込んだ
フードドライブをやったり
本当に、すごい方です。
お話をうかがっていると
そのすごい情熱や思いが
伝わってきて、こちらの胸もジーンと
熱くなったほどです。
人のために、誰かのために
あそこまで動ける人って
尊敬しますし、とっても素敵だと
思います。
私も見習わなければと思いました。
自分は、今の仕事を通じて
人のためや世の中のために
なれているだろうか?
人を笑顔にできているだろうか?
人を元気でポジティブな気持ちに
させられているだろうか?
などなど、
お話を聞いていると本当に
色々考えさせられました。
そういう意味では、
今の自分の在り方を問い直す
いい機会にもなりました。
素敵な機会を与えていただいた
Aさんに感謝です。
「Aさん、ありがとうございました」
「Aさんの今後の活動を陰ながら
応援しておりますし、私自身も
もっともっと社会に役立てる仕事を
していきたいと思いました!」
「感謝です!」
最後までお読みいただき
ありがとうございました。
今日も素敵な一日になりますように!
◆読者からの励ましの声が、
何よりもエネルギーになります。
あなたからの感想・コメント、
お待ちしています。
お気軽に、コメントください
info@feli-zes.biz
【本メルマガについて】
このメルマガは、
・働く人のヤル気であふれ
活き活きと働ける職場を作りたい
・働く人が持てる能力をフルに発揮しながら
成長してもらいたい
・成り行きではなく明確なビジョンを
持って、経営を進めたい
・経営者と従業員がそのビジョンに向かって
一体となって進んでいきたい
・仕事を通じて世の中に貢献したい
そんな中小企業経営者の皆さまや
企業経営に関わる方々にお役に立てれば
という想いで発行しています。
このメルマガでは、
自分自身のサラリーマン時代の経験や
実際のコンサル現場での経験などから、
日々感じたことを情報発信
させていただきます。
その中で、ワクワクドキドキ心動かす
企業・お店づくりのヒントを提供しながら、
お役に立ちたい。
そして自分自身も一緒に豊かな人生を
目指して成長していきたいと考えています。
メルマガへの想い詳細はこちら
https://www.felizes.biz/mailmagazine
◆フェリーゼス経営理念◆
ワクワクドキドキ、
働く人の人生を豊かにする
コンサルティング
◇フェリーゼスミッション◇
経営者と従業員が、
毎日会社に行くのが楽しみで仕方がない
ワクワクドキドキで一杯の
中小企業づくりをサポートします!
ご興味ある方、詳細はこちら
https://www.felizes.biz/aboutus
【公式サイト】
https://www.felizes.biz/
【個人Facebook】
https://www.facebook.com/atsushi.kanemoto.9
【公式ブログ】
https://www.felizes.biz/blog
(過去のメルマガもアップしています)
***************************************
心動かす企業経営
【発行元】フェリーゼス経営支援事務所
【発行責任者】金本 淳
経済産業大臣登録 中小企業診断士
豊田市働き方改革アドバイザー・講師 国際ファッション専門職大学非常勤講師
【住所】
〒480-1161愛知県長久手市荒田1-1-718
【お問い合わせ】 info@feli-zes.biz
=========================














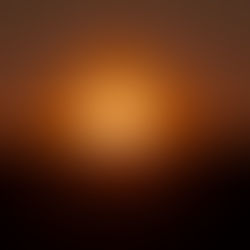









コメント